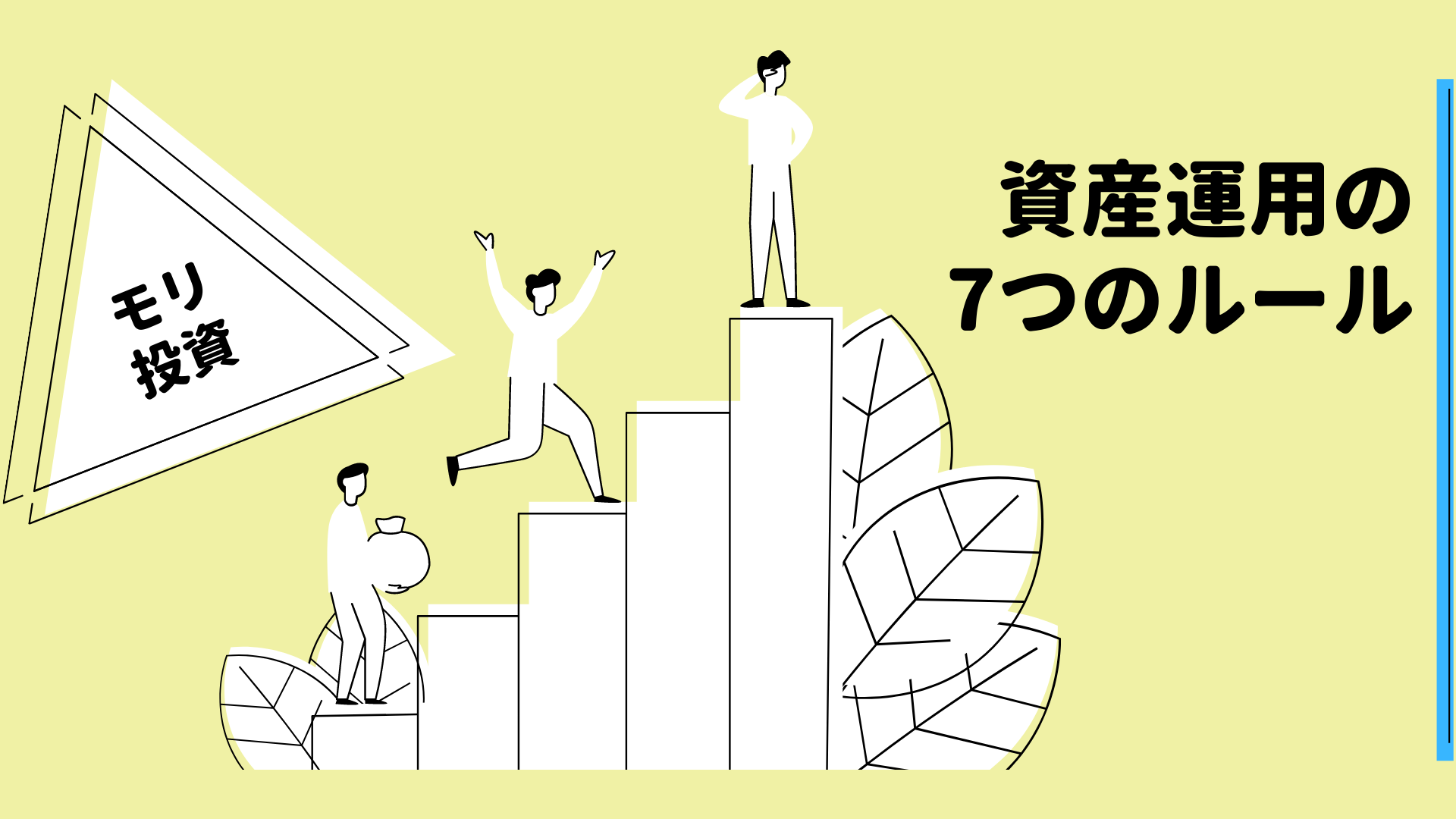↓良かったら応援クリックをお願いします!
こんにちは、モリ(@ijumori)です。
2020年11月から資産運用を始めました。
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。
投資を開始してから様々なことをおこなってきましたが、今後は一定のルールに基づいて投資活動の判断をしていこうと思います。
そこで今回は、今後の資産運用ルールを考えてみましたというテーマでお話をしていきます。
早速ですが、以下のルールを基本に資産運用をしていこうと思います。
- 毎月の収入の20%を貯金
- 生活防衛資金には手を付けない
- つみたてNISAで毎月33,333円積立
- 投資信託を16,667円定期積立
- 増加資金を再投資
- 損益がマイナス10%になったら損切り
- 毎月1日に運用成績の記録をつける
今回は私の資産運用ルールについてお話をしていきます。
資産運用ルールを考えてみた
これまでいろんなことを少しずつ試してきて投資の経験値を高めてきました。
またWebサイトや書籍なども参考にしてきました。
そこから考えた資産運用のルールは以下のとおりです。
- 毎月の収入の20%を貯金
- 生活防衛資金には手を付けない
- つみたてNISAで毎月33,333円積立
- 投資信託を16,667円定期積立
- 増加資金を再投資
- 損益がマイナス10%になったら損切り
- 毎月1日に運用成績の記録をつける
参考にした書籍は次の2冊です。
投資を含め資産運用において感情が入ると判断が遅れたり誤ったりする可能性が高まり、市場から退場しなくてはいけないようなこともでてきてしまいます。
そうならないためにルールを設けました。
では一つひとつ詳しく解説していきます。
資産運用の7つのルール
1.毎月の収入の20%を貯金
投資をするには元手となる資金が必要です。
私はサラリーマンをしているので、毎月の収入の中から元手となる資金を捻出します。
ただし、「収入 – 家計 = 運用資金」ではありません。
全額投資してたら、何かあったときに対応できなくなってしまいますからね。
そのため、本業と副業の収入を合わせた金額の20%を貯金とすることにしています。
額面20万円なら4万円、30万円なら6万円、40万円なら8万円というように。
初めにこのルールを設定したときは収入の10%を貯金することにしていました。
ですが貯金の割合を2倍にしました。
人の欲望には際限がありません。
そのため人はお金があればあるだけ使ってしまう生き物です。
初めから収入の8割しか使わないと決めれば、自分に本当に必要なもの以外には使わなくなり、これまでと大して生活水準を変えることなく生活していけます。
言い換えると、手元に残るお金を調整することで生活水準の膨張を未然に防ぐ効果が期待できるのです。
こうすることで一番やりたいことのためにお金を使うことができるようになります。
ある程度溜まったら資産運用や自己投資に回します。
2.生活防衛資金には手を付けない
生活防衛資金とは、不測の事態に備えた貯蓄のことをいいます。
いざというときにすぐに使えるお金です。
投資をしていない人には馴染みのない言葉かもしれません。
私はサラリーマンなので、病気やケガで休まざるを得ない状況だったり、リストラや失業をしてしまうと収入が途絶えます。
そのような不測の事態でも何とか生活できるように貯蓄したお金を生活防衛資金というのです。
生活防衛資金は条件によってどのくらい必要なのか異なってきます。
一般的に
- 独身サラリーマンは生活費の3ヶ月から半年分
- 自営業は生活費の1年から2年分
- 子育て世帯は生活費の2年から3年分
といわれています。
私の毎月の生活費は約23万円なので、なるべくリスクを回避するために半年分の138万円を生活防衛資金としています。
この138万円には一切手を付けずに現金として残します。
3.つみたてNISAで毎月33,333円積立
投資を始めるきっかけとなったのがつみたてNISAです。
つみたてNISAは年間上限40万円まで、20年間非課税で運用できるお得な制度です。
年間上限の40万円を毎月定額で積み立てます。
毎月の積立額は以下の通りとなります。
40万円 ÷ 12ヶ月 = 33,333円
私はつみたてNISAを楽天証券で 楽天カード によるクレジット決済にしています。
楽天カード のクレジット決済をすると
- 5万円まで利用可能
- 楽天ポイントを利用できる
- 100円につき1ポイント付与される
など、とてもお得なので 楽天カード によるクレジット決済にしています。
4.投資信託を16,667円定期積立
楽天カード のクレジット決済の上限額が5万円のため、つみたてNISAの33,333円を除いた16,667円を投信積立に当てています。
定期積立にしているので長期投資を目的にしています。長期で積み立てて複利効果を狙っています。
5.増加資金を追加投資
私は毎月1日に月次収支表をつくっています。
毎月の余剰金を追加投資するためのルールをつくりました。
それは、毎年の1月1日を起点とし、月末の収支の余剰金を5年分に分けて毎月の積立額に上乗せをするというものです。
例:8月1日時点で1月1日から60万円の余剰金ができたとします。
この60万円を5年分に分けて毎月の積立額に上乗せします。
60万円 ÷ 5年 ÷ 12ヶ月 = 1万円 を毎月の積立額に上乗せするということです。
120万円の余剰金が生まれていたら、
120万円 ÷ 5年 ÷ 12ヶ月 = 2万円 を毎月の積立額に上乗せするということです。
毎月つみたてNISAと投信積立で5万円積み立てているので、余剰金は追加投資となります。
あくまでも余剰資金に対して一定の割合を追加投資するということです。
生活防衛資金は手を付けないことにしているので、それ以外の純増額を追加投資に回すことにします。
ファンドのチャートの特徴により、積立指定日は毎月18日としています。
6.損益がマイナス10%になったら損切り
私は個別株も買付しています。
少額でいろんなことを試しながら取引しています。
いずれはポートフォリオの一定以上を株式で占めたいと考えています。
投資において、損小利大が理想のトレードと言われています。
また投資で最も大切なことは大負けしないこと、ともいわれています。
そのため損失を少なくするために損切のルールを設けます。
損益率がマイナス10%になったら損切をします。
一時的な下落で、もしかしたら上がるかもしれない。
けれどもっと下がるかもしれない。
感情で判断するのではなく、一律マイナス10%になった段階で売却をすることにします。
大きな損失を防ぐのです。
購入時に「逆指値売り注文」をしておくと、もし暴落をして株価が下がったとしても常に株価を気にせずに過ごせます。
7.毎月1日に運用成績の記録をつける
先述の通り、私は毎月1日に月次収支表をつくっています。
家計簿のもうちょっと複雑なものです。
月次収支表を作成する際に一月分の投資運用成績を記録しています。
つみたてNISAと積立投信に加え、個別株の売買をスプレッドシートにまとめています。
長期投資を目的にしているので、運用成績を意識せずに淡々と積み立てるだけなのですが、パフォーマンスがいいとやはりうれしいものです。
月次収支表では総資産額も管理しています。
ずっと右肩上がりで資産が増えているのでこのまま増やしていけるよう努めていきます。
まとめ
最後にもう一度、資産運用のルールを振り返ります。
- 毎月の収入の20%を貯金
- 生活防衛資金には手を付けない
- つみたてNISAで毎月33,333円積立
- 投資信託を16,667円定期積立
- 増加資金を再投資
- 損益がマイナス10%になったら損切り
- 毎月1日に運用成績の記録をつける
参考にした書籍は次の2冊です。
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから
「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ(@ijumori)でした。